「将来、子供の養育費は足りるのか?」
「今さら準備しても遅いのでは?」
このように、子供の養育費に対して不安に感じる家庭は少なくありません。
子供の養育費は誕生から大学卒業までに、最低でもおよそ2600万かかると言われています。
「まだ小さいうちは貯め時」といいますが、継続して貯められない家庭もあるのではないでしょうか。
そこで、将来の資産を形成する手段として、学資保険やジュニアNISAを考える方もいらっしゃると思います。
今回は、養育費を目的にするならどちらが必要で、おすすめかを説明したいと思います。
結論から言うと学資保険はおすすめしない

結論から言うと、学資保険はおすすめしません。
教育資金準備は、ジュニアNISAを利用したほうが良いと考えます。
学資保険とジュニアNISAで共通するメリットは、積み立てにより資産が貯まる(または増える)ことです。
そして、それぞれのメリット・デメリットを以下にまとめました。
メリット・デメリット
- 学資保険
- メリット:親に不幸があった場合の保険がある。
- デメリット:途中解約で損をする。保証を充実させると返戻率が悪くなる。
- ジュニアNISA
- メリット:非課税で子供の資産形成可能。非課税対象商品が多い。
- デメリット:2023年に制度終了。投資なので元本保証はない。
では、メリット・デメリットがざっくりわかったところで、ジュニアNISAをおすすめする理由を説明します。
ジュニアNISAをおすすめする理由
養育費としての資産形成を目的とするならば、
そもそも保険の要素は必要ないためです。
おそらく、生命保険に加入されている家庭がほとんどだと思われますので、
保険の要素により返戻率が下がるよりも、
純粋にジュニアNISAで効率よく資産形成するほうがお得です。
現状、学資保険の期待払戻率は約102-106%です。
100万円預けても6万円程度しかプラスにならないのは痛いです。
(ジュニアNISAの場合、より大きなリターンが期待できます。)
そして、学資保険では途中解約の場合は損をしてしまうのが致命的なデメリットです。
ジュニアNISAでおすすめの商品は?
おすすめしたい商品は、全世界株式インデックスファンドです。
具体的にはeMAXIS Slim 全世界株式といった商品となります。
別記事でまとめているので、以下をご参照ください。
子供の将来の養育費として長期保有が前提で、年率4%以上のリターンが期待できます。
よって、理論上は学資保険よりも高いリターンとなります。
2023年12月末でジュニアNISA制度終了

この制度終了が最大のメリットだと言えます。
制度廃止がメリットになる理由
2024年以降は、子どもが18歳になっていなくても売却が可能となります。
制度の廃止によって、18歳までの払出制限が2024年以降に撤廃されることになりました。
そのため、2024年以降は子どもが18歳未満であっても、いつでも払い出しができます。
長期保有前提ですが、いつでも払い出しできるのはメリットです。
制度終了後も、非課税で管理可能
結局のところ、これからジュニアNISAを開設するとしても、取引が3年間に限られます。
しかし、制度終了後も口座開設者の年齢が20歳になるまでは非課税で資産保有と管理が可能です。
ジュニアNISAで満額資産を積み立てた後は、そのまま保有し続けるのも手です。
2021年から始めても、80万円×3年=240万円は運用し続けられます。
240万円で15年間、年率5%の運用ができれば、かなりの教育資金となります。
どこの証券会社がおすすめか?
おすすめの証券会社は、ネット証券です。
ネット証券の中でも、SBI証券、楽天証券、マネックス証券の3社がおすすめです。
詳しくは別記事でまとめていますので、ご参照ください。
もちろん元本保証がないことはデメリットです。
長期保有が前提とはいえ、投資は自己責任でよろしくお願いします。

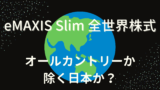



コメント